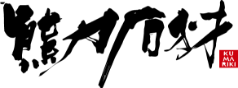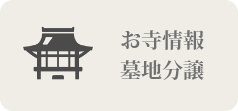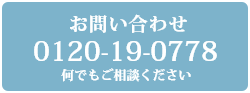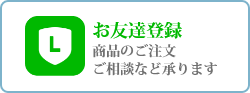有限会社熊力石材
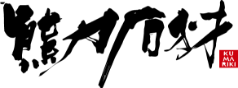
©2024kumariki.jp
お墓のこと
- Qなぜお墓を建てるの?
-
お墓には2つの意味合いがあると⾔えます。ひとつは故⼈を記念し、記録を永く保存して⼦孫に伝えるという意味です。
そのため⽊製の卒塔婆では⻑持ちしませんから、墓⽯が必要になるのです。
もうひとつは墓標とは故⼈の⼀⽣を象徴化してその⼈が持った意味を込めるものとされています。
- Qお墓を建てる手順は?
-
まず最初にしなければならないのはお墓をどこに建てるかを決めることです。 公営霊園の場合はまず申し込みをして抽選に当たらなければなりません。 さて寺院に墓所を欲しいという方はどうすれば良いのでしょうか。 まず墓所をお分け頂ける寺院の中から自分の気に入った寺院を選びます。 (もちろん宗派も考えますが、最近は自分の選んだ寺院の宗派に 改宗する方がほとんどです)
そして一般的にはその寺院の住職と面談をし、そのお寺の檀家になるために入檀の手続きをします。そして墓所を永代に渡って使用するために、寺院に「永代使用料」を支払います。それから墓石を選び、出来上がったら埋葬手続きを済ませた後、寺院の住職により お墓の「開眼供養」をしていただき、埋葬という手順になります。
- Qお墓を建てるにはどれくらいの費用がかかるの?
-
都内の寺院墓地の場合、大きさにもよりますが標準的な大きさのものですと、 墓所代・墓石代を合わせて300万円位が相場と言えるでしょう。 しかし最近では「小さめでもいいからもっと安く都内の寺院にお墓が欲しい」という人が増えてきているのを受けて、寺院でも一回り小さ目の墓所を 設けているところが少なくありません。
また石材も石の種類や大きさによってまちまちですが、国産の石材を使っても、 小さ目の墓所ですと200万円を下回るものもあるのです。
- Qお墓を建てるのにローンは利用できるのか?
-
できます。お墓も現金で支払うとなると、まとまった金額が必要になるものですから、ローンが必要とされるのも当然の成り行きでしょう。 ここ数年の傾向としてはローンを利用する方が増えてきています。
一般的には全額ローンではなく、内金をいくらか用意した上で残りを分割にするというケースがほとんどです。
- Q違う宗派のお寺にお墓を建てることはできるのか?
-
たとえばお葬式はキリスト教ですませて、お墓は浄土宗のお寺にお願いしても まず許可していただけません。
寺院とは仏の教えを研究し、広めるのが 本来の仕事で、お墓の管理を義務としているわけではありません。